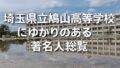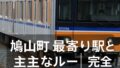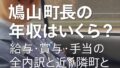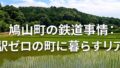鳩山町の鉄道事情:駅ゼロの町に暮らすリアル
埼玉県比企郡鳩山町は、町内に一つも鉄道駅が存在しない珍しい自治体です。人口約1万3千人のこの町は、都心から約50km圏に位置しながら、自然豊かな田園風景と整備されたニュータウンが同居しています。 この記事では「鳩山町 電車」をキーワードに、なぜ鳩山町に鉄道駅がないのか、その歴史的背景から、住民の通勤通学の実態、バスやデマンド交通などの交通施策、高齢者や学生への影響、他の鉄道駅がない自治体との比較、将来的な交通改善の可能性まで、網羅的に解説します。
鉄道駅が存在しない理由と歴史的経緯
鳩山町には鉄道路線自体が町域を通っておらず、町内に鉄道駅は一つもありません。この背景には地理的・歴史的な要因があります。鳩山町は周囲を丘陵に囲まれた地域で、かつて主要な鉄道幹線から外れていたため、鉄道が敷設されないまま発展してきました。
1970年代、日本では埼玉県東松山市を中心に大規模な「比企ニュータウン」計画が構想され、人口50万人規模のニュータウン開発が検討されました。それに合わせて東武東上線とJR八高線を結ぶ「比企・八高連絡線」など複数の新線計画が立案され、鳩山町を含む比企地域への鉄道延伸も夢見られていたのです。しかし、肝心の鉄道路線新設は実現せず、この壮大な計画は“幻”に終わりました。結果として、鳩山町には鉄道が通らないままとなり、以後は道路交通に依存した地域形成が進んだのです。
一方、鳩山町では1974年から「鳩山ニュータウン」の開発が始まりました。高度経済成長期のベッドタウン計画として民間主導で造成された大規模住宅地で、1990年代まで段階的に拡張されました。このニュータウン入居開始により町の人口は急増し、ピーク時の1995年には約1万8千人に達しました。しかしニュータウンには鉄道駅が設けられず、当初から東武東上線の最寄駅からバスでアクセスする前提の都市計画でした。その後、人口減少と高齢化が進行する現在でも、鳩山町には依然として鉄道駅がなく、住民は鉄道以外の交通手段で生活圏と都市圏を結んでいます。
開発から約50年が経過した鳩山ニュータウンでは、人口減少と高齢化の進行が顕著です。町人口の約52%がこのニュータウン地区に居住していますが、ニュータウン単体の高齢化率は55.5%に達しています。2017年時点でニュータウン地区の人口は7,263人(3,252世帯)と、ピーク時から減少傾向にあります。それでもニュータウンは現在も鳩山町の中核として機能しており、町の魅力と課題の両面を象徴する地域となっています。
最寄り駅と町外へのアクセス方法
町内に駅がない鳩山町の住民にとって、最寄り駅までのアクセスが生活の鍵となります。鳩山町の東側では東武東上線の高坂駅(東松山市)および坂戸駅(坂戸市)が、また西側では東武越生線・JR八高線の越生駅(越生町)が玄関口となっています。町内各地からは川越観光自動車(東武グループ)の路線バス4路線が出ており、これら近隣駅と鳩山町内を結んでいます。
高坂駅・坂戸駅方面へは主に東部ニュータウン地区からの路線バスが頻繁に運行されており(後述する鳩山ニュータウン線)、おおむねバスで10~20分程度で駅に出ることができます。坂戸駅から東武東上線急行に乗れば池袋まで約40分強で到達できるため、鳩山町から都心への通勤通学も十分可能な距離感です。一方、町西部の越生駅へは北部の上熊井地区などから町営バス(後述)でアクセスできます。
鉄道以外の交通インフラとして、道路網も確認しておきましょう。鳩山町内には高速道路や国道が一本も通っていません。しかし町境付近には関越自動車道の坂戸西スマートIC(坂戸市)や、圏央道の鶴ヶ島JCTがあり、自家用車で数分走れば高速道路網にアクセス可能です。そのため、自動車を利用する住民にとっては首都圏各方面へ比較的スムーズに移動できる環境が整っています。ただし鉄道駅や主要道路が町内にないことは、車を運転できない人々にとって大きなハンディキャップとなっています。
町民の通勤・通学手段と日常の移動実態
鳩山町民の移動手段は、自家用車とバスが二本柱です。鉄道駅がないため、多くの世帯が自家用車を所有し、買い物や通勤通院に利用しています。特に戸建て主体のニュータウン地区では車移動が日常化しています。一方、都心方面への通勤通学者や運転免許を持たない学生・高齢者にとっては、路線バスで最寄り駅まで出て鉄道に乗り換えるのが基本的な移動手段です。
実際、鳩山町は東京のベッドタウンとして発展した歴史から、通勤先・通学先が東京都という住民が非常に多い特徴があります。2010年国勢調査によれば、鳩山町から通勤通学する人の行き先は東京都区部が27.0%と群を抜いて多く、坂戸市、東松山市、川越市など埼玉県内主要市よりも東京への流出が多い状況でした。このため、朝の時間帯には高坂駅・坂戸駅行きのバスに乗り込み、その先の東武東上線で都心へ向かう通勤・通学風景が日常となっています。
町内の中学生までは町内の学校に通いますが、高校や大学進学となると多くは町外へ出ます。鳩山町内には埼玉県立鳩山高等学校がありましたが、2026年に越生高等学校との統合が予定されており、今後は町内で高校に通えなくなる見込みです。そうなると高校生も坂戸・高坂方面や越生方面へバスで通学することになり、朝夕の交通需要がさらに増えることが予想されます。実際、鳩山高校が存続していた間は、高坂駅~鳩山ニュータウン線の路線バスが朝7~8時台に1時間あたり5本、日中でも毎時4本運行されており、多くの高校生が利用していました。統合後は地元高校が無くなるため、町として通学手段の確保が課題となるでしょう。
また、町内には東京電機大学(鳩山キャンパス)や山村学園短期大学といった大規模な教育機関・研究施設が所在し、他地域から学生がバスで通学しています。このように、鳩山町は町外へ出る通勤客と町外から来る通学者の双方がバス輸送に依存する土地柄と言えます。
日常的な移動について見ると、買い物・通院など生活のための移動手段も重要です。町内には大型商業施設が少ないため、隣接する坂戸市や東松山市のショッピングセンター・病院へ自家用車で出かける住民が多くいます。一方、免許を持たない高齢者などは路線バスや後述するデマンドタクシーを利用して買い物や通院をしています。もっとも、路線バスの停留所から離れた集落も多く、徒歩圏にバスがない地域の住民にとって移動手段の確保は深刻な問題です。2010年時点で、町内人口の約29%がバス停から300m以上離れた地域に居住しており、こうした“公共交通空白地帯”では自家用車に依存せざるを得ない状況が続いています。
鳩山町内を走るバス路線
鉄道の代替として、路線バスは鳩山町の公共交通の主役です。町内を走る一般路線バスはすべて東武グループの川越観光自動車が運行しており、現在以下の系統があります:
-
鳩山ニュータウン線(高坂駅西口~鳩山ニュータウン):鳩山ニュータウン地区と高坂駅を結ぶ幹線路線。途中、物見山登山口、こども動物自然公園、大東文化大学(東松山市内)などを経由し、ニュータウン内のサブセンターやニュータウン中央停留所を巡回します。平日朝は鳩山高校入口まで乗り入れる便も運行され、通学対応が図られていました。
-
坂戸駅~大橋線(坂戸駅北口~大橋):坂戸市街地から鳩山町中央部に至る路線です。「大橋」は鳩山町内のバス停留所名で、町役場や鳩山中学校の最寄りです。この路線により、坂戸駅と鳩山町中心部(大橋地区)が結ばれています。
-
東京電機大学線(高坂駅西口~東京電機大学):高坂駅から鳩山町南東部の東京電機大学キャンパスへ直行する路線です。通学時間帯を中心に運行され、大学関係者の重要な足となっています。
-
入西団地線(北坂戸駅~入西団地~鳩山ニュータウン):北坂戸駅から坂戸市入西(にっさい)地区および鳩山ニュータウンを結ぶ路線でした。現在は経路変更により、鳩山ニュータウン線に統合され「鳩山ニュータウン~今宿」間の延伸が行われています。
以上の民間路線バスに加え、鳩山町が運営する町営路線バス(コミュニティバス)も存在します。町営バスとして現在運行されているのは「高坂駅~上熊井~越生駅」線で、いわゆる北部線ルートです。この路線は町北部の上熊井地区など公共交通空白地域の解消を目的に、2016年に実証運行が開始されました。高坂駅西口とJR八高線・東武越生線の越生駅東口を結び、平日4往復程度運行されています。途中、大橋(町役場前)で前述の民間バス路線(坂戸駅~大橋線)と接続し、乗り換えが可能です。
以前はこれとは別に、町内を循環するコミュニティバス(鳩山町内循環バス)も運行されていました。循環バスは1989年(平成元年)に白ナンバーの町営バスとして運行開始し、石坂地区など移動需要の高い地域を定時定路線で巡回していました。しかし、デマンドタクシー普及による利用者減少や非効率な運行が課題となり、住民アンケート等での意見を踏まえて2022年3月末をもって廃止されています。現在は先述の町営バス北部線とデマンドタクシー(後述)に役割を引き継いでいます。
バス路線網のカバー率については前述の通り課題が残りますが、主要なニュータウン地区では比較的本数も確保されています。鳩山ニュータウン線はニュータウン住民の足として一日あたりの運行便数が多く、平日昼間でも概ね1時間に2本程度、朝夕ラッシュ時は増便されてきました。一方、町外へ出る目的が少ない昼間時間帯や休日の便は限られており、本数の少なさを指摘する声もあります。また、夜間帯(最終バス)の早さも課題で、以前から「坂戸駅~大橋線の最終を繰り下げてほしい」「高坂駅~鳩山ニュータウン線を北坂戸駅へ直通させてほしい」といった要望があったものの、十分に実現できていない状況です。
それでも、路線バスは町民にとって欠かせない生活インフラであり、町はその維持に力を入れています。川越観光バスの路線維持のため、行政が運行補助金を支出したり、高齢者向けの割引乗車証を発行したりするなどの支援策も講じられています。通勤通学でバスと鉄道を乗り継ぐ人が多いため、効率的なダイヤ編成や乗り換えの利便性向上も地域公共交通計画の中で検討されています。
交通不便がもたらす課題と町民の声
鉄道駅がないことによる交通の不便さは、鳩山町の暮らしにいくつかの課題をもたらしています。まず挙げられるのが、高齢者や免許を返納した人々の移動手段の確保です。先述のように町内の公共交通網は限られており、バス停が遠い地域では移動そのものが困難になります。高齢者にとってはバス停まで歩くこと自体が負担で、不便だとの声も寄せられています。
また、通勤・通学者にとっても、バスと電車を乗り継ぐ現在の生活には制約があります。例えば深夜に都心から戻る場合、終電で坂戸駅に着いても鳩山町方面への終バスが無く、自宅までタクシーに乗らざるを得ないことがあります。雨天時や荷物が多い時に駅から自宅まで距離があると不便さが際立つとの指摘もあります。さらに、町内に企業や大型商業施設が少ないため日中に町外へ移動する必要があるケースも多く、運転できない主婦層からは「日常の買い物にも車が無いと困る」「気軽に出かけられる交通手段がもっと欲しい」との要望が聞かれます。
こうした交通不便による課題は、町の人口動態にも影響しています。若年層の中には「車がないと生活しづらい」という理由で他地域への転出を選ぶ人もおり、結果として鳩山町の高齢化率は2020年時点で45.9%と県内最高水準に達しました。町の幸福度ランキングが全国1位になったことも話題になりましたが、その調査報告でも「交通アクセスの不便さ」が町の課題の一つとして挙げられています。住民アンケートでも、交通利便性の向上は常に上位の要望となっており、行政もこれを重く受け止めています。
高齢者・学生など特定層への影響と工夫
鉄道空白の町で真っ先に影響を受けるのは、移動弱者とも言われる高齢者層です。鳩山町では65歳以上人口が町民の約半数を占めており、高齢ドライバーの免許返納も年々増えています。車に頼れなくなった高齢者の足をどう確保するかは行政の重要課題です。その解決策の一つが後述するデマンドタクシー「はとタク」ですが、その他にも買い物弱者対策として移動販売車の導入や、ボランティアによる送迎サービスの検討など、様々な工夫がなされています。例えば、鳩山町ではスーパーマーケット(コモディイイダ)と連携し、高齢者や障がい者、子育て世帯を対象に移動販売車で日用品や食料品を届ける試みを行っています。これにより、交通手段が乏しい方でも自宅近くで買い物ができるよう支援しています。
学生への影響も見逃せません。中高生は基本的に公共交通か保護者の送迎に頼るしかなく、特に高校生は前述のように町外の学校へ通うケースが多いため、早朝・夕方のバスに集中します。バス会社と学校が協議して臨時便を出すなどの対応も行われていますが、長期休暇中の減便やダイヤ変更により不便を感じる生徒もいるようです。また、小中学生についても、鉄道で遠方の塾や習い事に通う場合はいったん坂戸・高坂までバスで出なければならず、都市部のように電車だけで移動できない不便さがあります。こうした事情から、学校や地域では地元で完結する活動(例えば町内での習い事や交流イベント)を充実させ、子どもたちの過度な移動負担を減らす工夫も模索されています。
一方で、町内にキャンパスを構える東京電機大学の学生たちは高坂駅から大学直行バスを利用しています。こちらは大学とバス事業者の連携で増便が図られており、講義時間に合わせた便が設定されています。大学生の場合、自家用車で通学する人も一定数いますが、キャンパスの駐車場収容台数に限りがあることから公共交通利用が推奨されています。鳩山町としても大学との協定の中で、学生が地域のデマンドタクシーに登録しやすくする施策などを検討しており、若者にも公共交通を利用してもらう取り組みを進めています。
鳩山町の交通政策:コミュニティバスからデマンド交通へ
こうした交通課題に対処するため、鳩山町はこれまで様々な交通政策を講じてきました。中でも特徴的なのが、全国的にも先進例となったデマンド型交通(乗合タクシー)の導入です。
先に触れた町内循環バスは、高齢化と利用低迷により2022年に運行終了しました。その代替として本格展開されているのが、予約制の乗合タクシー「はとタク」です。はとタクは町内在住の利用登録者を対象に、自宅から目的地まで相乗りで送迎するデマンド交通サービスで、2009年(平成21年)に実証運行を開始しました。当初は町内限定・平日昼間のみの運行でしたが、利用者の支持を受け徐々にサービス拡充が図られています。
現在のはとタクは、町内であればドアツードアでどこでも1乗車200円という格安運賃で利用できます。さらに、町外の埼玉医科大学病院(毛呂山町)や坂戸市のにっさい(入西)地区、東上線北坂戸駅への乗降も可能で、それぞれ300~600円の定額料金で運行しています。利用には事前予約が必要ですが、電話一本で自宅前まで車が迎えに来てくれる利便性から、高齢者を中心に「生活の足」として定着しています。2022年4月からは土日運行も開始され、さらにAIを活用した配車システムによる効率化も進められました。運行は地元の越生タクシーに委託されており、町は年間約4,000万円(一般会計の0.7%)のコストでこのサービスを支えています。町民からは「200円でどこでも行けるので助かる」「免許返納後の移動手段として安心」という声が多く、アンケートでも高い満足度が報告されています。
また、鳩山町は埼玉県のスマートシティモデル事業の一環として、新たなモビリティサービスにも積極的に取り組んでいます。例えば、電気自動車(EV)を活用したカーシェアリング拠点の整備や、買い物代行サービスとの連携によるMaaS(Mobility as a Service)の構築などです。将来的には、自動運転シャトルや高齢者向け小型モビリティ(電動カート等)の導入も視野に入れ、地域の交通弱者に優しい「スマートモビリティ」社会を目指しています。
さらに行政は、近隣自治体との広域連携にも注力しています。坂戸市や越生町とは公共交通の接続強化について協議を行い、デマンドタクシーの乗降可能エリアを相互に拡大する取り組みも検討されています。これにより、町境を越えた移動の円滑化や、広域病院へのアクセス改善が期待されています。また、鳩山ニュータウン地区では住民ボランティアによる送迎サービスの仕組み作りも議論されており、行政だけでなく地域コミュニティ全体で交通を支える意識が芽生えつつあります。
他の「駅がない自治体」との比較
鳩山町のように鉄道駅が一つもない自治体は、全国的に見ると決して珍しくありません。北海道の広大な町村や離島部を除いても、本州各地に同様の市町村が存在します。例えば、埼玉県内では鳩山町を含めて7つの町村(小鹿野町、川島町、松伏町、三芳町、吉見町、東秩父村)が鉄道駅ゼロの自治体です。これらの多くは郊外のベッドタウンや農村地域で、やはり住民はバスや自家用車に頼った生活を送っています。
お隣の川島町(人口約2万人)は鳩山町と同じく最寄りの鉄道駅までバス連絡を強化しており、東武東上線若葉駅やJR高崎線桶川駅への路線バスを運行しています。川島町でもコミュニティバス「かわじまくるりんバス」を巡回させる一方、デマンド型交通「かわしま号」を導入しており、高齢者の足を確保しています。吉見町(人口約2万2千人)も東松山駅・鴻巣駅方面への路線バスに加えて予約制乗合タクシーを運行し、買い物や通院の利便性向上に努めています。埼玉県東部の松伏町(人口約3万人)では、町独自に「らくらくMoving」というライドシェアサービスの社会実験を行い、バス路線のない地域での交通確保策を模索しています。
首都圏近郊では埼玉県と千葉県に駅のない自治体が複数ありますが、鉄道駅の数で比較すると千葉県の方が多く(千葉県336駅、埼玉県230駅)、埼玉県の人口規模を考えると駅に恵まれない地域が相対的に多いとも言われます。それだけに埼玉県内の各自治体は独自の工夫で交通不便の解消に取り組んできました。三芳町(人口3.8万人)では長らく鉄道空白が課題でしたが、近隣のふじみ野市との境界付近に東武東上線の新駅誘致(「みずほ台」駅と「鶴瀬」駅の中間)が検討された時期もありました。しかし実現には至らず、現在は路線バスと自家用車による輸送が中心です。三芳町も高齢者向けに100円バスを走らせたり、デマンド交通の試験導入を行ったりしています。
全国的な視野で見ると、地方では過疎化に伴い鉄道路線そのものが廃止され「鉄道空白地帯」となった自治体も増えています。その中で成功例として語られるのが、岐阜県八百津町です。八百津町は駅がない代わりに町営バスを高度化し、需要に応じて乗合タクシーと組み合わせるハイブリッドな交通モデルを確立しました。また、神奈川県愛川町(人口4万人)も町内に駅がなく、最寄りの小田急線本厚木駅までのバス便を増強したり、コミュニティバス「あいちゃんバス」を複数ルート運行したりすることで対応しています。愛川町は工業団地も抱えるため、通勤バスの運行や、鉄道駅の無い町同士(清川村など)の連携による交通ネットワーク構築にも取り組んでいます。
このように他自治体の事例を見ると、「駅がない」=「不便な町」と一概に決めつけられない面もあります。行政や地域の工夫次第で、住民の移動ニーズを満たす代替交通を用意し、快適に暮らせる環境を作り上げている地域も少なくありません。鳩山町も全国幸福度ランキングで上位に入るほど住民満足度が高い町ですが、その裏にはデマンドタクシーなど交通面の地道な努力が支えていると言えるでしょう。
将来的な鉄道誘致・交通改善の可能性
最後に、鳩山町に将来鉄道を誘致したり交通環境を大幅に改善したりする可能性について考えてみます。結論から言えば、現時点で鳩山町に新たな鉄道路線や駅を誘致する具体的な計画はありません。人口減少や財政制約を考えると、新線建設のハードルは非常に高いのが現実です。1970年代のニュータウン計画時に描かれた鉄道新線も、結果的に実現しなかったことを振り返れば、今後単独の町で鉄道誘致を成し遂げるのは容易ではないでしょう。
しかし、交通改善の芽が全くないわけではありません。鳩山町は「コンパクトシティ+ネットワーク」構想のもと、拠点を絞り込んだまちづくりと交通ネットワーク再編を検討しています。具体的には、鳩山ニュータウン地区を中心に高齢者が生活しやすい都市機能を集積し、その周辺をデマンド交通やコミュニティバス、そして将来的には自動運転シャトル等でカバーするビジョンです。国の地方創生施策やスマートシティ支援を活用しながら、持続可能な地域交通のモデルを築くことが期待されています。
また、周辺市町との広域交通連携も鍵となります。例えば、東武東上線の坂戸駅周辺の再開発によってパークアンドライドの駐車場が整備されれば、鳩山町民が車で坂戸駅まで行き電車に乗るという「自動車+鉄道」のハイブリッド通勤がより促進されるでしょう。さらには、将来的に東武越生線やJR八高線の高度化(BRT化や電化による高速化)が図られれば、越生駅経由の都心アクセス時間短縮も考えられます。技術面では、空飛ぶクルマやドローンタクシーといった新モビリティが実用化すれば、鉄道に頼らない移動の選択肢が増える可能性もあります。もっとも、こうした未来の乗り物が日常化するには時間がかかるため、当面は地に足の着いた交通サービス改善を着実に進めていくことが現実的です。
鳩山町は駅がないハンディを抱えつつも、住民・行政・事業者が一体となって知恵を絞り、様々な交通手段を駆使することで日々の暮らしを支えています。その姿は他の鉄道空白地のモデルケースとも言え、注目を集めています。鉄道駅ゼロの町であっても、人々が安心して移動でき、快適に暮らせる環境を整えること――鳩山町の挑戦はこれからも続きます。そのリアルな姿から、交通政策に携わる者や移住検討者は多くの示唆を得られるでしょう。